
「FAXって存在してたんだ!!?!」

はじめまして、はたぼーです。
4年勤めたIT企業を辞め、地元で親が経営している工場に入社した初日の感想です。
お客様からの注文書や仕入先からの納品書、請求書がすべて紙。
仕入先へ段ボールを注文するにしても手書きで注文書を作成し、FAX。
IT会社員時代ではメールやチャットツールで業務が簡潔していた身としては驚き以上に
「(アナログ)許せねぇ・・・」という感じでした。
とはいえそんな環境でも会社として売上が立っているので、
郷に入ったばかりの立場では何も言えず。
小さいことから始められる
それでもこっそりとすこしずつ、
納品書、注文書をデジタル化していきました。
「あのネジいつ買ったっけ?納品書で探して!」
→調査に5分(探しきれず諦めることもある)
[かかった時間]5~10分
「段ボール注文しておいて、いつものやつ!」
→仕入先を特定するのにに5~10分。注文書作成に2分
[かかった時間]5~10分
これらがこうなりました↓
「あのネジいつ買ったっけ?納品書で探して!」
→検索でHIT、過去の注文履歴がすべて確認でき、単価の値上げ額も分かる
[かかった時間]2分
「段ボール注文しておいて、いつものやつ!」
→仕入先に紐づいた資材を即特定、注文書を自動作成し、プリンターで印刷
[かかった時間]2分
一つ一つの削減時間は僅かですが、年間に換算するとかなり効いてきます。
10人や30人規模、小さな会社であるほどインパクトがありますよね。
中小企業がDXを推進する意義
- 業務効率化とコスト削減
手作業や紙ベースのプロセスをデジタル化することで、時間・人件費の削減やミスの防止につながる。在庫管理や受発注をデジタル化すれば、作業負担を軽減しながら正確さを確保できる。
- 人手不足への対応
日本の中小企業は特に人材不足が課題。
DXによる自動化・省力化は、少人数で回せる仕組みを作り、持続的な事業運営を可能にする。
- 顧客満足度の向上
データ活用により顧客ニーズを把握しやすくなり、一人ひとりに合ったサービスや商品提案ができる。ECサイトやSNSを活用すれば、従来の商圏を超えて新たな市場開拓も可能。
- 競争力の強化
大手企業はすでにDXを進めており、対応が遅れると取引先から選ばれなくなるリスクがある。
逆に早めに取り組めば、大企業との差別化や新規取引の獲得につながる。
- 新しいビジネスモデル創出
製造業ならIoTで稼働状況を見える化して保守サービスを提供するなど、付加価値のある事業展開が可能。
データ分析を活用すれば、従来にないサービスや商品の開発につなげられる。
- レジリエンス(変化への強さ)の確保
コロナ禍で明らかになったように、突発的な社会変化に迅速に対応できる体制が重要。
DXによってテレワークやオンライン販売を整備すれば、有事でも事業を継続できる力が備わる。
大規模な設備投資や高額なコンサルタントに依頼するよりも、
継続して続けられて、効果も見込めるのはDXの大きな特徴と言えます。
思わぬ副次効果
具体的な実例を紹介します。
社長がお客様に提示する、商品の卸値を見積もっているときのこと。
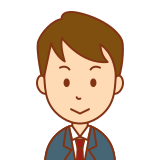
見積もりが全然捗らない~~
弊社はBtoBのため、商社に商品を卸しています。
卸値を計算するには、材料費、工賃、運賃、その他諸経費をもとに計算します。
この計算が間違っていると、卸先のお客様にとって高すぎと感じられたり、
逆に安すぎて儲けにならない、ということが起きます。
見積もりを適当にやるとそのような悲しい事故が起きます。
価格は1~2年変更できず、後で適正価格から大きく反れてると気付いてもどうすることもできません。
だからこそ時間をかけて丁寧に見積もりをするのですが、
材料原価の計算には、
「どのネジが何本使われたか、1本あたりいくらか?」
「どの塗料が何ml使われたか、1Lあたりいくらか?」
これらの調査を紙媒体の納品書(仕入れ品を記録する帳面)から調査していました。
商品点数が200点ほどあると、なかなか進まないというわけです。
そこで、当時使用していたkintone上で納品書アプリを作りました。
内容はシンプルで、過去1年程度に仕入れた品目を仕入先毎に単価も含めすべて記載したもので、
kintoneの標準検索機能で一瞬で検索できる、というものです。
結果として、社長には大変喜ばれました。
ページをペラペラめくって探すよりもずっと早く単価を割り出せるので、
見積もりの役に立ったとのことでした。
卸先のお客様としても、忙しいカタログの更新時期に一日でも早く単価が分かると、
それだけ改稿作業が進むというわけで、恩恵を受ける関係者が多かったと振り返ります。
そもそもDXとは?
「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の略称。
デジタル技術を駆使して、業務プロセス、製品・サービス、組織文化までを含めた根本的な変革を行うことです。
意味は広く、IT企業に勤めている人でもDXを正確に説明できない人がいます。
ペーパーレス=DXという解釈をしている方がいらっしゃいますが、
DXはそれだけではありません。
製造業の現場でいいますと、
紙の作業指示書を、ネットに常時接続しているタブレット上で表示することで
リアルタイムでやるべき作業が明確になり、無駄な検討時間が減る。
結果、お客様へ商品をお届けする時間が短縮され、顧客満足度が向上する。
上記の例では、作業書はプログラムにより自動で作成され、
管理職の稼働が削減されます。
作業者としても、やるべきことがはっきりとし、無駄な稼働、残業が少なくなります。
このようにDXは、単一の作業や部門の効率が上がるだけでなく、
企業の生産活動全体に効果を与える可能性があります。
デジタル化の広いやつ、と思ってください。
しょぼいDXで何を目指すか?
こんな仕事はPCにまかせてしまおう、というのが根幹にあると思います。
弊社では以下のようなことが常態化していました。
・仕入れ額の計算を電卓で行い、請求書との突き合わせを行う。
・現場への指示が紙ベースで行われ、進捗状況は現場に見に行かないと分からない
・仕掛品含む資材の在庫管理ができていないので、欠品が起こりあたふたする
・毎月書いている報告メールを毎回手打ちしている
小さいことも書けばきりがありませんが、
このような無理・無駄を減らすことができれば、
社員の教育に時間をかけたり、追われているお客様のクレーム対応の処理などに
時間を有効活用できます。
昨今の目覚ましいAIの発達も、DX化を後押ししてくれます。
人手不足で中小企業の踏ん張りを試されている中で、
生成AIは頼りになるツールです。是非フル活用しましょう。
本ブログでは、生成AIの利用が頻繁に出てきます。
使い慣れていれば仕事でも、プライベートでも活躍しますので、ぜひ覚えましょう!


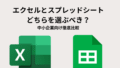
コメント